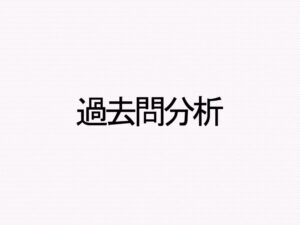2025年1月実施FP1級学科試験分析(基礎編)
お待たせしました!!
今回もスピード重視で試験問題を分析します!
今回も初見問題結構ありました!!⊂⌒~⊃。Д。)⊃
テキストに載っていない問題はこの場で出来る限り解説しています。
問題の判定は基本的には以下の3つ。
当テキスト未掲載などで、正解を導き出すのは困難だった問題「難問」、
当テキストから正解を導き出せるものの、難易度が高かった問題「普通問」、
当テキストが身についていれば問題なく解けたであろう「易問」。
ただし、問題の難易度から判断する場合もあります。ご了承を。
FPWikiでは公式テキストじゃなく、当テキストで勉強していたことを基準としております。
今回もきんざいの問題用紙を片手に読み進めてください。公式サイトから印刷もできます♪
急いでアップしたので間違った解説があったら教えてくださいね!すぐ修正します。それとリンク切れとか誤字脱字も!!
ご指摘はXか当サイトのお問い合わせページでぷりーず(ノД`)・゜・。
それとこの企画のコンセプトがぼやけてきてしまったのであらためて。FPWikiの過去問分析はみんなとわいわいするためです。FP試験勉強は孤独になりがち。SNSでフォロワーさんたくさんいる人はそうでもないかもしれませんが、FP試験、特に1級はまわりに受検してる人はほとんどいないよね。自分はこの問題はこう思ったけどみんなはどうだったんだろう。とか、ここ難しかったよねぇ、これは簡単だった!みたいな受けてきた感想のようなものをみんなで共有できたらいいなって思って解いています。なので、わたしもできる限り受検生視点で解きます。受検勉強の箸休めというか、楽しみにしてもらえたらうれしいです。
書籍版ご利用者のために該当ページを載せてみました♪
応用編の分析はもう少しおまちください。がんばりますっ!!
このページは基礎編の解説です。
基礎編の検証
問 1
易問 正解2
6つの係数の問題。FP1級は係数を複数使ってくるのが定番になってきてますが、今回は係数こそ複数ですがストレートな問題でしたね。当てないといけないところです。年金原資を計算するのは年金現価係数を使います。15年間800千円ですので、800千円×12.8493=10,279,440円です。これを貯めないといけない。
積立期間は20年を指定してきています。目標額を貯める時の積立額を決めるのは減債基金係数です。つまり10,279,440円×0.0412=423,512円ですね。
千円未満は切り捨てなので、423千円が正解となります。
毎回書いてますが、年金現価係数だの減債基金係数だのと名前を覚えるのが苦手な人は以下の方法で考えてみてください。
★ちなみに、暗記が苦手でどうしようもない!という人には暗記せずに正解する方法があります。余談です。
たとえば、80万円を15年受け取りたい。通常計算で80万円×15年=1,200万円です。ですが年2%運用ですから少しお得になる。つまり貯める額は×15より少なくていいハズです。
表の中からそれっぽいものを探すと・・・、12.8493の年金現価係数かぁ!となるワケです。
逆に、20年間いくらずつ貯めればいいですか?なんて問題の場合もありますね。この場合は通常計算でいけば100%÷20年=0.05なわけですが、これも年2%運用が効いてきますね。つまり0.05より少なくていいハズ。
また表の中からそれっぽいものを探すと・・・、0.0412の減債基金係数かぁ!ってなる訳です。
6つの係数暗記するのムリ!!って方はこの方法で導いてください!!ヾ(≧▽≦)ノ
02.6つの係数p11
問 2
難問 正解1
なんと通勤災害の一部負担金が出ました。もう社労士です。200円を超えない範囲で定められているのですが、ここまで覚える必要がFPにあるのか?この辺りの範囲が増えてくるようであればテキスト入りを検討したいと思います。FPに200円の事が心配で質問するお客さん・・・いますかね?んー。
ちなみに業務中の災害は会社に補償義務があるため当事者が負担する必要がないんですって。なので通勤時のみ負担が必要になるとの事です(^^)/
他の選択肢はすべてテキスト掲載済みです。ですから知らずとも消去法で正解に辿り着けますが、今回は難問としておきます。
問 3
易問 正解3
パパママ育休プラス問題。夫の育児休業開始日前に妻が育児休業開始しちゃうと制度が利用できません。
テキストの注意書きの部分が出題されました。大事な事ですもんね。実務的な良問だと思いました(^^)/
06.雇用保険 p32
問 4
易問 正解3
障害認定日に判定となりますので選択肢3は適切ですね。請求できません。
問 5
普通問 正解3
不適切は3。遺族基礎年金は設例の通りなのですが、遺族厚生年金は夫が55歳以上である必要がありますので第二順位である子が受給します。ネット上では間違った解説してる人が散見されます。ご注意を!
問 6
難問 正解2
適切は2番。中退共に事業主が新規加入する際に従業員の勤務期間を通算できるのは最大で10年まで(120月まで)となります。テキスト範囲外です(>_<)いれます
ただし、その他の選択肢はすべてテキスト対応済みで、かつ、難しい選択肢はありませんでした。選択肢3は4か月目から1年間なので少し引っ掛けですかね。良く出る引っ掛けです。難問としておきますー。
問 7
難問 正解3
適切は3番なのですが、テキスト外でした(ノД`)・゜・。
国民年金基金は私的年金なんですけど、自営業者等の2階部分の年金となるため(サラリーマンで言う厚生年金)公的性格が強い年金です。税制は国民年金と同等となりますね。
選択肢1は好きな方を選べるので不適切。
選択肢2はこれまたテキストに記載なし・・・。これ前にも出題されたと思うんだよなあ。受け取った年に一括ではなくそれぞれの年に当てはめて計算できます。じゃないと所得税率が高くなっちゃうもんね。累進課税の国ですから(>_<)
選択肢4は相続人本人の一時所得ですね。実務してる保険屋さんとか銀行員さんは強いかも。
と、いう事でテキスト対応不充分の問題でした。難問とします!
06.一時所得・雑所得・山林所得p257
09.所得控除p267
問 8
難問 正解4
これまた細かいところがでました・・・。日本学生支援機構の授業料後払い制度は対象が大学院生もしくは専門職過程となっていますね。4が不適切となります。
選択肢1と2はテキスト記載アリ。選択肢3は金利選択でテキスト記載なしでした。固定金利と変動金利が存在します。これは・・・少し盛り込みます(>_<)
18.教育資金支援制度p85
問 9
難問 正解4
これまた完全にテキスト外。令和3年7月開始の「生命保険契約照会制度」でした。これは、加入者本人が死亡、認知、災害で行方不明などの場合に、遺族親族等が加入状況を確認するには大変だったわけですが、生命保険協会に届け出れば一括照会ができるというもの。3,000円で利用出来て2週間程度で回答がくるということでとても便利です。
選択肢1は適切。財形保険、財形年金、支払開始済みの年金保険、据置保険契約は対象外となります。
選択肢2も適切。本人に聞けなくなっちゃった状況が必要ってことですね。
選択肢3も適切。利用できる人は死亡時の場合だと、法定代理人、法定相続人、遺言執行人など相続できる権利を持っている人になりますね。
選択肢4は不適切。さすがに手続きまではやってくれないですね。
この問題についてはテキスト入りはいったん様子を見ます。出題が続くようならテキスト入りを検討いたします(^^)/
問 10
易問 正解1
クーリングオフの問題です。これはストレートな問題でした。適切は1番。保険期間1年以内の短期契約は対象外です。
契約転換は新たに入りなおすことなので対象。契約更新は対象外。ちなみに特約付加も対象外です。
01.保険契約者保護機構p93
問 11
普通問 正解4
いくつあるか問題で、またも0が正解という選びにくい心理攻撃問題でした。これ、本番受けた人はほんと嫌だよね( `ー´)ノ
(a)は5倍に達するまでですね。
(b)どちらかを受け取った時点で消滅しますね。
(c)これが一番いやらしかったですかね。日本語がわかりにくい。保険期間が経過して残り期間が短くなると収入保障保険の受取総額は低下しますね。伝える気がない文章のような印象を受けますね。
03.生命保険等商品p98
問 12
易問 正解2
珍しく保険料控除問題が!!いまさらまだ出るのか!!これだからテキストから外せないんだよな・・・。
さて保険料控除。新制度は生命・介護医療・年金でそれぞれ4万ずつ、合計12万が最大なのですが、昔は保険と年金の2分類のみで5万ずつ。合計10万円でした。
対象の加入時期の保険がそれぞれある場合、好きな方が選択できるようになっています。
今回の例だと、医療と年金だけに加入の人。てことは新制度だと最大8万にしかなりませんね。契約時期が古い(2011年以前)ので医療保険のほうも旧制度5万円にして合計10万円にしたいところですが・・・。保障内容欄を見ると2018年に更新となっています。テキストで説明していますが、主契約の更新は新制度になってしまいます。つまり医療保険は4万円が最大。この場合も年金は旧制度をそのまま利用できますので、
4万円+5万円=9万円
正解は2番になります。
04.生命保険料控除p105
問 13
難問 正解1
これも難問かなぁ。適切は1番でテキスト外でした。地震保険は店舗併用でも保険料に差異はないというものです。
他の選択肢はすべてテキスト掲載です。でも難しい選択肢が多かったかなぁ。
特に4ですが、50%と70%が反対ですね。うろ覚えの人には厳しい出題のされ方ですね!当てた方はすごい!!(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
07.火災保険と地震保険 p120
問 14
易問 正解3
自動車保険の任意保険の問題。不適切は3番。ノーカウント事故は確かに1等級上がるのですが、窓ガラスの破損はそもそもノーカウント事故にはならず、車両保険を使うと1等級下がります。
08.自動車保険 p125
問 15
易問 正解2
損害保険の税金の問題。ポイントとなるのは2番と3番ですかね。2が適切(正解)なのですが、お店に問題があって出た保険金。これは課税対象です。3は身体に問題があって個人の所得補償として支払われたもの。これは非課税となります。そして4はお店の倉庫が燃えて商品が補償された。これは課税です。事業に関するものは基本は課税。身体に関するものや個人に関わるものは非課税が多いです。この辺、同じ損害保険の税金とはいえ別物なので、FPWikiではカテゴリを分けて解説しております。ご参考になればと思います。
10.(個人)損害保険契約の税金関係p133
11.(事業)損害保険の経理処理p135
問 16
普通問 正解1
適切は1番で遅行系列ですが、他の選択肢がいつもと違って変化球ぎみでした。選択肢2はFP2級Wiki掲載なのでご覧ください。
02.景気・物価指標 p142
02.経済指標(FP2級Wiki)
問 17
易問 正解1
不適切は1番。ファミリーファンドは顧客は赤ちゃんにならないといけないので購入するのはマザーファンドじゃなくてベビーファンドですね。お母さんたくさんいたら大変ね(^^)/
03.投資信託の管理と運用(運用側)p146
04.投資信託の販売商品(顧客側)p150
問 18
易問 正解4
これは債券投資の基本的な問題でした。イールドカーブは右上がりが順イールドですね。ロールダウンは逆イールドが強くなるほど効果があります。
デュレーションは早く利益回収できるほうが短くなるので割引債じゃダメ。表面利率が高いほうがいいし、残存期間が短くて早く元本戻ったほうが短くできるんです。
よって正解は4番です。
07.債券利回り計算p159
問 19
易問 正解3
選択肢4のラッセル2000指数のみテキスト未記載でした。ラッセル・インベストメントが出している指標で、上位2000ではなく1001~3000位で構成されています。3番のナスダックが適切ですね。S&P500は時価総額加重平均型。ダウ工業株平均は30種ですね。ラッセル指数のテキスト入りは少し様子見です(^^)/
01.株式マーケット指標p140
問 20
難問 正解1
今回の株式投資の計算問題は新たな出題でありました!難問です。
サスティナブル成長率を求める問題で「やった!」って思った人も多かったと思います。でも〈資料〉を見ると「?」という難問。
サスティナブル成長率を求めるには、ROEと配当性向が必要ですね。配当性向はある。でもROE算出のための当期純利益や自己資本の項目は無し・・・。
「自己資本の額は純資産の額と同額である」となっている場合、過去問でEPSとBPSから求めるものがありました。またこれか?と見てみるもその項目も無し・・・。
仕方ない、資料を深く見ていきましょう。「株価収益率」とはPERですね。PERと書けよと。「株価純資産倍率」はPBRです。そう書いといてよ。
ここで初めての情報になるのですが、PBR=PER×ROEで表すことができるというものです。すみません、知りませんでした。
当てはめてみると、0.80=12.80×Xとなりますので、
12.80X=0.80
X=0.80÷12.80
X=0.0625
6.25%
これでROEが出せました。あとは公式に当てはめます。
サスティナブル成長率(%)=ROE×(1-配当性向)
6.25%×(1-0.35)=4.0625=4.06%
以上が計算方法となります。
大変勉強になりました。なりましたが・・・これをテキスト入りするかどうか。今回は悩まされるものが多いです。
掲載しなければ解けない問題ではありますが、この解法が頻出するだろうか。そして実用的であるのか。その判断が難しいです。少し検討させてくださいm(_ _)m
10.株式投資の企業分析p175
問 21
易問 正解1
これは簡単でした。バリア条件をつければオプション料は安くなります。他の選択肢もテキストのとおりです。
17.デリバティブ取引「オプション取引」p197
18.店頭デリバティブ取引p201
問 22
易問 正解3
相関係数=証券AとBの共分散÷(Aの標準偏差×Bの標準偏差)
相関係数=9.80÷(4.75×5.85)
=0.3526
よって選択肢3の0.35が正解です。これはもうそのままストレートな問題。該当ページを何度も読んで試して覚えてもらうしかないですね(^^)/
20.ポートフォリオ効果 p209
問 23
難問 正解4
テキストにほぼ網羅されておりましたが、選択肢3のみ漏らしていました。金融機関変更は実務的にも欲しい情報です。ひとまずWEBサイトに加えさせていただきました!
正解は4番で、海外転勤する際にも所定の手続きを取っておけば引き続き保有ができます。・・・が、購入はできません(ノД`)・゜・。難問に修正しましたm(_ _)m
問 24
難問 正解2
投資者保護基金からの問題でした。FPWikiでは軽くしか解説していないので難問認定となってしまいました。信用取引の保証金や各種証拠金が保証されますが、外国先物やデリバティブ取引などは対象外となっていますね。
25.セーフティネットp228
問 25
易問 正解4
選択肢3はパッと見だと適切に見えてしまいますが、配偶者ではなく子となっているので86万ではなく50万です。あとは特に悩む点はないかなぁ。選択肢1が突然低価法なのでえ?え?何か記憶違いしてるかも?!ってテンパった人はいたかもしれないですね。でもしっかり学習している人なら冷静に4番を選んだと思います。
03.不動産所得・事業所得p245
問 26
易問 正解1
この問題はテキストのままですね。1が不適切で休職期間があっても在籍期間として計算します。ですから不適切ですね(^^)/
4は5年未満の役員ですから通常ではなく2分の1されない退職手当として計算します。こちらは適切です。
04.給与所得・退職所得p251
問 27
易問 正解4
損益通算の問題はとてもオーソドックスな問題が出ました。富士山上(不・事・山・譲)が対象となります。しかし、不動産所得は土地の取得に要した負債利子は通算できません。また、譲渡所得は生活に必要なものに限ります。よって、不動産所得は▲100-20=▲80万円。譲渡所得は金地金なので対象外です。雑所得は元々対象外。不動産と事業所得を通算します。
▲80+300万=220万円
総所得金額は220万円となります。
08.損益通算(実践編)p264
問 28
易問 正解3
住宅ローン控除の問題。これも基本的な出題でしたね。年間所得2,000万以下が対象となります(^^)/
最長で13年だし、店舗併用住宅でもできるし、所得税から引けない分は住民税から引きますよね♪
10.税額控除p274
問 29
難問 正解3
げ!またもFPWikiテキスト範囲外(; ・`д・´)
なんか今回だいぶやられてる~。みなさんに申し訳ないm(_ _)m
法人税法上の益金不算入問題。この辺はほとんど出ないんですけどね。
国税庁のHPによると「基準日以前1月以内に取得した事実及び当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡」となっておりますので、3が不適切となります。
FPWikiに掲載されているのは選択肢1のみ・・・です。
問 30
難問 正解2
なにこれ交際費も深堀問題?!(; ・`д・´)
今回基礎編簡単だったって声が多いけど、変化球多くないですか?そんなに甘い回ではなかったのでは?
適切は2番。取引先への災害見舞金ですって。下にリンク貼っておきます。わたしはこれは捨て問にします。
問 31
難問 正解2
法人税の資産の評価損。これまた偏ってる・・・。選択肢2の棚卸資産の評価損が適切です。季節商品の在庫にも「棚卸資産の著しい陳腐化の例示」が該当します。ただし、季節が過ぎても販売実績が高いとダメとの事ですね。それにしても今回試験のD分野は国税庁HPから出題されているのかな・・・?
問 32
難問 正解2
個人住民税は賦課課税方式なんですが、法人住民税は自分で申告する申告納税方式なんですよねー。なんかうまいことテキストのすき間を突いてきてる感じがします(>_<)
なんて、それはFPWikiのおごりですよね。きんざいがこの弱小サイトを意識してるはずはない。単純にテキストにまだまだ穴があるということ。精進します!!
20.法人住民税・法人事業税p312
12.個人住民税・個人事業税(FP2級Wiki)
問 33
易問 正解4
急に易問ですね。簡易課税制度の定番、2種類以上の事業を行っていてその一つが売り上げの75%以上を占めれば全体に適用ができます٩( ''ω'' )وやったー
21.消費税p313
問 34
易問 正解3
登記事項要約書の交付は窓口に限られます。
01.不動産登記 p321
問 35
易問 正解1
正しいものはひとつですね。(a)が適切です。(b)は2倍を返還します。(c)は超えた分が無効となります。易問です。
03.不動産売買の注意点 p328
04.宅地建物取引業法p332
問 36
易問 正解2
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の問題。賃料の増減をしない特約は有効です(^^)/
05.借地借家法p335
問 37
易問 正解3
これまた易問。合計床面積5分の1以下の駐車場は延べ面積に算入しなくて済みますね(^^)/
08.建築基準法(道路・用途・高さ)p344
09.建築基準法(建蔽率・容積率)p348
問 38
易問 正解4
これも良く出る計算問題。基準は固定資産額で、その2分の1。そして税率は3%。FPWikiの過去問チャレンジはやってくださってますか?(^^♪
12.不動産の取得と保有にかかる税金 p357
問 39
普通問 正解3
適切は3です。家を建て替えようと思ってハウスメーカーに依頼したら年をまたいだってケースですね。これで急に固定資産税が本則で取られたらたまらないですよね。状況を想像して常識的に考えたらわかる問題なのですが、テキストにはズバリ記載はありませんでした。
1,2,4はそれぞれテキストで確認できます。特に4ですが特定空家認定を受けると翌年度から適用できなくなりますが、まだ措置をするように指導をうけた段階なので不適切となります。うろ覚え斬りですね。FPWiki学習者は消去法で辿り着ける問題です。普通問となります。
12.不動産の取得と保有にかかる税金 p357
問 40
易問 正解1
これは定番問題ですね。でも定番過ぎて最近出てなかったのでハズしてしまった方もいるかな?空家の控除と3000万特別控除は併用できます。でも合わせて3000万円なので注意ですね(^^)/
それと相続税の取得費加算は併用できません。
14.居住用財産の譲渡の特例p367
問 41
普通問 正解1
これほんとは定番のDCF法の問題なんですが、うまく6つの係数を絡めて出題してきてて、迷彩問題となっています。DCF法ですから現在価値に割り引いて計算するものです。表にはたくさんの係数がありますが、知りたいのは原価。使うのは結局は現価係数のみ。FPWikiテキストの「複利原価率」と「現価係数」は同義です。あとはテキスト通り。
2000万×0.952+2000万×0.907+2000万×0.864+3億円×0.864=3億1,366万円
よって1が適切です。ストレート問題をうまく難易度調整したような感じですね。テキストずばりでしたが普通問としておきます(∩´∀`)∩
19.投資用不動産の評価方法 p381
問 42
普通問 正解4
4が不適切。「夫が所有」する財産を譲り受けているのでその譲渡時の時価となります。この問題もいつもとだいぶ毛色が違いますね・・・⊂⌒~⊃。Д。)⊃
1,2はそのままテキストどおり。3も居住用財産の譲渡ですからもちろん適用できますよね。
04.贈与税の配偶者控除p402
問 43
難問 正解2
令和6年に改正された相続時精算課税制度についての問題でした。その中で土地又は建物の特例からの出題でした。FPWikiでは軽くしか触れてないんですよねm(_ _)m
どういう特例かというと、相続時精算課税で先に不動産をもらったんだけど、相続が開始するまでの間に災害にあって不動産価値が下がってしまった時に、その被害額は相続額から引いていいよっていうものなんです。本来は贈与時の価額で計算するのが相続時精算課税制度なのですが、これは被災者にやさしい、良い特例ですよね。
さて、不適切は2番。贈与を受けた日から災害が発生した日まで所有してることが条件。・・・そりゃぁそうだよねぇ(*´Д`)
自分が被災してないと受けられないよねぇ。これはテキストにはないけど当てて欲しいところですねぇ。
でも1番がいやな選択肢。一見正当に見えますが「相続開始までの災害」ではなくて「相続税の申告期限までの災害」が正当です。ヤな感じですよね(ノД`)・゜・。
05.相続時精算課税制度 p404
国税庁PDFファイル→0024005-164.pdf
問 44
普通問 正解3
3が適切です。負担付贈与なので負担価額を控除しても良いということで、テキストに明確な記載はないのですが、これまた感覚的には当てられた問題かと。
1は放棄者がいても割り当ては増えないです。2は10年。3年は過去の生前贈与の算定年数です。4は死後の放棄は許可不要ですね。消去法でも正解に辿り着けます。
01.贈与と法律・贈与税p392
09.遺留分p416
問 45
易問 正解4
ほぼほぼテキスト掲載の易問でした。ちなみに選択肢3ですが、特別寄与者というのは相続人の範囲内ではないけど親族である必要があるので内縁は認められないですね。
問 46
普通問 正解2
(a)は基礎控除計算。人は重複しない。放棄者も数える。よって頭数は妻B、長男C、長女D、孫F、孫Gの計五人。3000万+600万×5=6000万です。適切。
(b)は2割加算。孫Fは2割加算。孫Gは代襲相続しているので対象外ですね。母Iですが、相続人から外れているのですが、相続人かどうかは全く関係なく、1親等の親族は2割加算対象がいなんです。ですから父母は対象外なんですね。いい問題です。
(c)は法定相続分。長女Dは相続放棄をしているので孫F、長男C、孫Gの3人で、ぱっと見6分の1ずつに思えますが、孫Gは権利重複しているので、孫Fと長男Cは8分の1ずつ、孫Gは4分の1となります。適切。
よって(a)(c)が適切なので正解は2となります。
06.相続分・寄与分・特別受益・養子縁組 p407
14.相続税の算出と納付税額p432
06.相続税の総額計算p502
問 47
易問 正解4
金融資産の相続税評価です。1~3までは不適切。すべてテキスト掲載です。4が適切となります。4は生命保険の税金のページから外貨建て保険の知識が流用できます。課税時期のTTBとなりますね。
05.個人の生命保険の税金p109
17.金融資産の評価p448
問 48
難問 正解2
これまた初出の問題ですねー。1のみ記載アリで、私道は自用地評価額×0.3ですね。そのほかの選択肢はいままでにないものでした。難問とします。
正解は2番。これまた国税庁のリンク貼っておきます。
18.不動産の評価(相続税評価額)p451
造成中の宅地の評価|国税庁
問 49
普通問 正解1
これは選択肢1が適切。なにやら迷彩はしてありますが、相続開始直前に同居していた親族なのでOKです。条件に当てはまります。
選択肢2が難問。基本居住していないとダメなわけですが、建て替え中であってもその後居住の用に供することが認められればOKです。
選択肢3は申告期限までに条件を満たしておけばOKです。
選択肢4は申告期限までに事業を営んでないとダメ。
19.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例p456
問 50
普通問 正解2
正解は2番。自由に譲渡できない株式です。1は逆で会社が株主に対して行使できます。3はすごく正解に近いですが、評価額に拒否権は影響しません。4は普通決議ではなく特別決議で決まります。
23.会社法p475
基礎編まとめ
今回、初見問題が頻出でした!!('Д')
対して既出問題はストレートな易問が多かったような印象。
すごく両極端な感じ。集計が気になるところです。
改めて分類の基準はこちら
当テキスト未掲載などで、正解を導き出すのは困難だった問題「難問」、
当テキストから正解を導き出せるものの、難易度が高かった問題「普通問」、
当テキストが身についていれば問題なく解けたであろう「易問」。
時折例外はありますが基本は上記基準でつけさせていただいております。
さて、今回の難易度分析を見てみましょう!!
集計結果!! 易問:24(前回21) 普通問:11(前回21) 難問:15(前回8)
やはり今回は初見問題が多く、難問増加!!対して既出問題は易問多数で両極端な結果に!!
結局これ、何点になるのか?
いつもの分析法で「到達点」を出してみます。
(易問正解率100%、普通問50%、難問25%で集計)※難問はただの確率(4分の1)で加点ってこと
つまりFPWikiを使ってしっかり学習をしていたら・・・で予想する平均点のようなものとご理解ください。
易問48点、普通問11点、難問7.5点=66.5点!!
今回の基礎編の到達点。あれ?結局集計してみると「最高得点かも?」といった前回の基礎編とほぼ同じ得点になりました。捨て問も多かったですが、残る問題数でも充分高得点が狙える状況だったということですね。SNSで今回はやさしめと言っていた意味が集計するとわかりました。
結局は取れる問題を落とさない。基礎をしっかりやってきたものが勝利を掴めるのが学科試験基礎編なんですよね。
今回、消去法でもたどり着けない完全サポート外問題は約10問でした。合格ラインは60点なんですけど、40問で勝負して28問当てるってことなんですよ!(捨問10問のうち選択問題なので2問は当たるよね、なので30問じゃなくていいのよ)なので28÷40=70%。つまりテストで70点目指すようなことなんです。そんなに無茶な話じゃないんですよね。突拍子もない問題が多いんで、対策どうしたらいいんや!って思っちゃうんですが、結局はそういう問題は無視して、しっかり基礎問題で70点取れる子を目指すのが近道なんです。
とにかく!!合格点に到達したみなさん、おめでとうございます!それは偶然ではない努力の成果ですよ!
今回基礎編が残念な結果だった皆さん。まだ修練が不足しているか、もしくはFPWikiを中心に学習していない・・・?( ̄ー ̄)ニヤリ
しっかり地に足つけて!基本に忠実に!次に向けてがんばっていきましょう!!
今回の基礎編、気になるのは初見問題。これは今回だけのたまたまなのか。それともこの先方針展開をしていくのか。んー、目が離せません!!
さぁ、ひと息ついたら今度は応用編の分析も見てください!!٩( ''ω'' )و