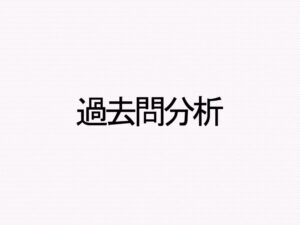2025年9月実施FP1級学科試験分析(応用編)
はじめに
2025年9月実施のFP1級学科試験の応用編を振り返っていきます。
基礎編まだ見てない方はこちら→2025年9月実施FP1級学科試験分析(基礎編)
毎度、基本的な話ですが応用編は5部構成。B分野リスク管理を除き(B分野かわいそう)
以下の構成で出題されます。
第1問 Aライフプランニング
第2問 C金融資産運用
第3問 Dタックスプランニング
第4問 E不動産
第5問 F相続・事業承継
今回も試験問題を片手にご覧ください。
分析の便宜上、配点予想もしていますが、
私の配点予想は過去の試験から想像したあくまでも独断です。
他のサイトさんを参考にもしてません。完全なる独断です。
みなさんは他のサイトの予想も参考にしてくださいね♪
そして急いで作っているので間違っている点があったら教えてくださいね(*´Д`)
また、ここは当てて欲しい!という問題は確定点と位置づけて難易度の指標にしています。
確定点の評価基準は「FPWikiで学習しているFP2級合格者」を想定しています。
それではいってみましょう。
応用編解説
第1問:ライフプランニング
問51
まずは穴埋め問題からスタート。配点は1問1点の計7点と予想。
健保の傷病手当金と労災の休業補償からの出題。割と答えやすいかも?ラッキー回か?
答:①3(日間) ②1年6カ月 ③8,000(円) ④60(%) ⑤20(%) ⑥傷病補償年金 ⑦7(級)
Ⅰ 健康保険の傷病手当金
①:傷病手当金は4日目からの支給ですよね~。慌てて4!って書かないように落ち着いて。
②:受給期間は最長1年6ヶ月ですね。これも基本。
③:標準報酬月額÷30日×3分の2です。8,000円ですね。ここは計算が入るので少し難しいですかね。
Ⅱ 労災保険の休業補償給付
④:60%ですねぇ。そこに特別支給の20%が加わって8割補償されるんですよね。
⑤:上と同じ解説です。この辺のところはサラリーマンの方は知ってる人多いですよね。ブラック企業勤務の人ほど詳しかったりして・・・ね?( ;∀;)
⑥:労災は雇用保険とか健康保険と違ってずっと補償が続きますからね。傷病補償年金に移行します。
⑦:7級ですね。記述式なのでここが難易度高かったですかね。7級までは年金形式、8級以下は一時金形式です。
問51は今回やさしかったです。全問正解もイケると思います。⑦だけちょっぴり細かいので確定点6点としておきましょうかね('ω')ノ
03.健保・国保・後期高齢者制度p14
05.労働者災害補償保険(労災)p25
問52
障害給付に関する出題。こちらの穴埋めは全部で5つ。配点は各1点、計5点と予想。今回のように問52まで穴埋めで、問53を年金試算にする回と、問52が年金試算で問53を穴埋めにする場合とあるんですがなんでなんでしょうねぇ?毎回記事を執筆する側からするとめんどくさ・・・(失礼)。
答:①3分の2 ②1(年間) ③831,700(円) ④1.25(倍) ⑤65(歳)
① :前々月までに3分の2以上納付している必要がありますね。
②:現在暫定的に直近1年間をちゃんと納めてればいいよってなってます。ちょっと細かい論点。
③:今年の年金満額です。ヤーさん居んな!です。831,700円。
④:障害等級1級は1.25倍。この辺は押さえてると思います。
⑤:加給年金。65歳未満の配偶者がいれば加算されます。ちなみに後から結婚してもOK。ありがたいですよね。
ここも割かし簡単でしたね。スムーズな出だしで落ち着いていけてるんじゃないでしょうか?確定点4点としておきましょう(^^)/
問53
年金試算です。今回は遺族年金相談編ですね。
それでは対策ページに沿って進めていきましょう。
私の配点予想は①②が3点ずつ、③が2点の合計8点とします(式に部分点あり)。
今回遺族年金生活者支援給付金の分、回答が多くて点数が分散してるので③を落とした人は不利になりますね。
答 ①1,310,300(円) ②394,632(円) ③65,400(円)
①遺族基礎年金の年金額
遺族基礎年金のほうは満額支給ですからまずヤーさん居んな!ですね。831,700円。そこに子ども2人です。兄さん急さ!239,300円ずつ。
831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円
ここはもう計算問題と言うより暗記に近いですね。金額を覚えていれば勝ちです。
②遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)
つぎは遺族厚生年金の計算。遺族厚生年金のポイントは、金額が4分の3になっちゃうことと、加入期間が短い人のためにみなし300月ってのがあること。Aさんは厚生年金は245月しか加入していないのでみなし300月で計算してあげます。いつもだと総報酬制導入前と導入後で計算して足し合わせるのですが、今回のAさんは若くてその必要はないですね。導入後の加入期間しかありません。簡単です。
320,000円×5.481/1,000×300月×3/4=394,632円
基本に忠実な問題。今回加点が小さいから①と②はやさしいのかな?
③遺族年金生活者支援給付金の額(年額)
はいどーもー。ここはFPWikiの応用編対策「年金試算」を見てくれていたかどうかだけで決まりますね。見てますかー?!え?見てない・・・?そうね、最近みんなあまり見てくれてないわね。みんなキャンプ道具揃えてキャンプ場のほうに行ってるみたいだからね( ;∀;)ガンバリマス
さて、ここはもうテキストそのままです。
5,450円×12ヵ月=65,400円
今回の年金試算は基本に忠実でした。暗記物に近い出題です。満点取って欲しいな。③を落としちゃった人はFPWikiに戻っておいでよ(^^)/マッテルヨー
確定点は満点8点とします。
01.年金試算p478
第1問のまとめ
第1問の確定点は合計18点。良い感じですね。FPWikiテキストが役に立ってる感じする。良かった。基礎編でどうなるかと思ったよ。この調子でいきましょう!
第2問:金融資産運用
今回も上場株式と投資信託への投資について悩むAさんの問題。いつも悩んでるね、Aさん。年に3回は悩んでるAさん。
問54
配当割引モデルとROEの問題ですね。配当割引モデルは応用編では少しレアですかね。
配点は各1点、合計5点としました。
答:①2,000(円) ②5,000(円) ③3.75(%) ④0.21(回) ⑤1.41(倍)
Ⅰ 配当割引モデル
①:定額配当モデルとは当テキストで言うゼロ成長割引モデルの事です。計算式は問題文にもある通りで
理論株価=1株あたり予想配当÷期待利子率
こういうことです。1株あたりの予想配当とはつまり、配当金を株数で割れば出ますから、表から拾うと2400÷24=100円ですね。
100円÷5%(0.05)=2,000円ということですね。ゼロ成長で考えたらぁ株価2,000円ぐらいのもんじゃぁん?ってことです。
②:続いて定率成長配当割引モデル。定額配当モデルに対していやいやこの会社これから大きくなるんだぜぇ?って要素を組み込みます。式はこう。
理論株価=1株あたり予想配当÷(期待利子率-期待成長率)
100円÷(5%-3%)=5,000円
成長率3%が加わったことで価値が上がりましたね。
③:サスティナブル成長率の問題。まずはROEから求めていきましょう。
ROE=当期純利益÷自己資本×100
自己資本とは株主資本+その他の包括利益累計額です。
ROE=6,00÷(89,500+6,500)×100=6.25%
続いてサスティナブル成長率です。式はこう。
サスティナブル成長率=ROE×内部留保率(1-配当性向)
配当性向とは配当金÷当期純利益で、どれだけ利益を配当金に回してくれたかってことです。2,400÷6,000=0.4ですね。
サスティナブル成長率=6.25×(1-0.4)=3.75%
このようになります。
Ⅱ 自己資本当期純利益率
自己資本当期純利益率はROEです。
④:使用総資本回転率です。3指標分解は基本なので必ず押さえておきましょう。売上高÷使用総資本(資産)で求めます。
28,400÷135,000=0.21回
⑤:こっちは財務レバレッジ。使用総資本(資産)÷自己資本です。自己資本はさっきもでました株主資本+その他の包括利益累計額です。
135,000÷(89,500+6,500)=1.41倍
ここはどうでしょう?結構余裕じゃないですか?満点いけたと思うんですが、配当割引モデルのほうが満点取れなかった人がいたかもしれないってところで確定点は4点としておきましょう。満点取れなかった人は配当割引モデルのページも学習してみてね(^^)/
03.財務データ分析p488
12.配当割引モデル計算p183
問55
たまにでる個別元本計算と、ポートフォリオの問題。ちょっとだけひねってるけど、当てられなくもない。
配点予想は各1点の計5点とします。
①12,000(円) ②11.600(円) ③20.315(%) ④トラッキングエラー ⑤シャープ(・レシオ)
Ⅰ 個別元本の計算
①:毎回30万ずつ買っていくのを加重平均すれば良いのです。例えば第1回の価格は9,375円で買えるので、30万円÷9,375円=32口を購入したってことです。
これを全5回やると、総口数は125口となります。投資資金合計は150万円ですから、150万円÷125口=12,000円が正解です。
②:600円の分配金のうち400円が特別分配金になったのでその分元本が割れます。12,000-400=11,600円が正解です。
③:これは預金利息等といっしょで20.315%です。20%って書いちゃった人、いるかなぁ。
Ⅱ パフォーマンス評価
④:これは最初面食らいますが、後半にインフォメーションレシオの解説があるので、そこでインフォメーションレシオとトラッキングエラーが結びついたハズ。
⑤:シャープレシオの解説ですよね。ポートフォリオのイロハのイがシャープレシオですから解説文でピンとくるくらいになりましょう。
ここも全部いけそうな勢いですが、本番の緊張でパフォーマンス評価のほうで落とす可能性もあるかなぁ。確定点4点にしておきます(^^)/
05.投資信託の実務p155
22.ポートフォリオのパフォーマンス分析p218
問56
なんと今回も来ましたポートフォリオ(期待収益率・標準偏差)!!
配点予想ですが①②ともに式3点、答え2点の合計10点(式部分点あり)。
答 ① 1.87(%) ② 0.89
①投資信託Yの標準偏差
実績収益率から求める標準偏差はちょっとレアですね。19.ポートフォリオのリスク計算p205のおまけのところをご覧ください。
①サンプルの平均値を出す。
(9.20%+6.20%+4.70%)÷3=6.70%
②サンプルと平均値の差を求め、それぞれ二乗する。
(9.20%-6.70%)²+(6.20%-6.70%)²+(4.70%-6.70%)²=6.25+0.25+4=10.5
*二乗すると負の数もすべて正の数になり平均がデフォルメされます。
③出た答えをサンプル個数で割ります。これが分散となります。
10.5÷3=3.5
④分散に平方根を掛ければ標準偏差が出ます。
√3.5=1.870828.....=1.87(小数点第3位四捨五入)
以上になります!!
②投資信託Yと投資信託Zの相関係数
相関係数の式はこうですね。
相関係数=投資信託YとZの共分散÷(Yの標準偏差×Zの標準偏差)
となると先に共分散を求める必要があります。
共分散は普段ならそれぞれの予想収益率と生起確率でもって計算していきますが、今回は実績がでてますので、この場合は①の問題と同じく単純にYとZを掛け合わせて3期分足していって平均する作業になります。
Yの実績収益率の平均値は6.70%でしたがこれがつまりYの期待収益率です。期待と言うか実績なのですでに結果なんですが。Zの分も出しましょう。
(6.10%+5.50%+3.70%)÷3=5.10%
3期で5.10%の実績だったってことですよね。
3期合計の実績からの計算なので生起確率(さてどれが起こるでしょう?)ではありませんからそこは抜いて共分散の式を作ります。ただしこのままだと3倍になってしまう(3期すべて足されてしまう)ので最後に3で割る必要があります。
第1期(9.20-6.70)×(6.10-5.10)+第2期(6.20-6.70)×(5.50-5.10)+第3期(4.70-6.70)×(3.70-5.10)=
2.50×1.00+-0.50×0.40+-2.00×-1.40=2.50-0.20+2.80=5.10
5.1÷3=1.70
これが共分散です。ここまでわかれば相関係数の式が使えますよね。相関係数=投資信託YとZの共分散÷(Yの標準偏差×Zの標準偏差)ですね。
Yの標準偏差は①の答えの1.87ですね。
1.70÷(1.87×1.02)=0.89126.....=0.89(小数点以下第3位四捨五入)
これで完成となります!!
珍しい実績収益率の問題で2問。ここはなかなか厳しかったですね。②は応用を効かせないと解けない正に応用編!!
確定点はテキスト完全解説ありの①を当てて②が部分点の確定点7点としておきます!!
この手の問題が続くようであれば②の問題もテキスト入りを考えたいと思います。
08.ポートフォリオ(期待収益率・標準偏差)p507
19.ポートフォリオのリスク計算p205
20.ポートフォリオ効果p209
第2問のまとめ
確定点は15点です!!まずまずですね(^^)/この調子でどんどんいきましょう♪
第3問:タックスプランニング
さて今回は法人じゃなくて個人のほうですね。落ち着いていきましょう。
問57
住宅ローンの相談です。これは身近なので覚えやすいところですよね?各問1点の計5点予想です。
①13(年間) ②2,000(万円) ③5,000(万円) ④19(歳) ⑤5(%)
①:住宅ローンは現在最長13年ですね。基本です。
②:総所得は2000万円以下。これも基本。
③:子育て世代が優遇されるんですよね。5000万円になります。ここは新しいので難しかったかな?
④:19歳未満の扶養親族を有しているのが条件ですね。
⑤:5%ですね。これは以前から変わりませんが細かいところでした。
ここは3問当てておければ充分合格ラインですね。できれば4つですね。確定点は3点といたします。
10.税額控除p274
問58
ここは式2点答え1点で予想配点9点としました(式は部分点あり)。
①3,950,000(円) ②3,800,000(円) ③12,700,000(円)
①退職所得の金額
退職所得控除の計算です。20年で800万円。それ以上は1年70万円で計算します。1年未満は繰上げて計算します。23年となります。
退職所得の金額=(退職金-退職所得控除額※)×1/2
{1,800万円-(800万円+210万円)}×1/2=395万円
04.給与所得・退職所得p251
②事業所得の金額
事業所得は単純。以下の式になります。
所得金額=総収入金額-必要経費
必要経費とは売上原価、販売費、一般管理費、その他所得を生ずべき事業について生じた費用などです。売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は6種類の原価法から選択しますが、届出をしない場合は最終仕入原価法になります。設例では届出なしなのでこれにあたります。売上原価は仕入高から年末棚卸高の最終仕入原価法での金額です。
1200万円-520万円=680万円
売上高1440万円-値引返品30万円-680万円-必要経費350万円=380万円
このようになります。
03.不動産所得・事業所得p245
③総所得金額
総所得計算です。総所得計算ですからすべてを足していきますねー。
まず給与。1030万は収入ですからこれを所得にします。速算表みて控除します。それと問題文に所得金額調整控除もって書いてあります。給与収入850万円を越える人(1000万円以上の人は1000万円で計算)は超えた分の10%を引いていいよってやつです。この人むかつくけど1000万超えてるんで1000万円で計算しますから1000万-850万で150万円。150万×10%で15万円控除できます。
1030万円-195万円-15万円=820万円
次に配当所得もありますね。70万円だそうです。配当所得はこう。
配当所得の金額=収入金額-株式等を取得するための借入金の利子
配当所得は、原則として総合課税(特に非上場株は)となっているので加える必要があります。負債利子はないというので引くものはありません。源泉徴収されている所得税はあとで考慮されますが所得としては70万円です。
あと事業所得ですね。②で計算した通りですので380万円を加える必要があります。
最後に退職所得。これは分離課税です。総所得とは別で計算します。理由はテキストでも述べていますが、日本は累進課税制度なので、加えてしまうと給与所得とか他の税率まで上がってしまうんですね。なので分離課税となっています。ですからここでは加えません。
380万円+820万円+70万円=1270万円
02.利子所得・配当所得p242
03.不動産所得・事業所得p245
04.給与所得・退職所得p251
ここは満点はさすがに難しそうですね。所得金額調整控除とかねー。忘れちゃいそうだよねー。
ということで確定点6点です
問59
課税総所得金額計算からの申告納税額計算問題です。前回、略式別表四だったので交互にでてきますね。
配点予想は各1点、合計6点とします。
答 ①380,000(円) ②1,830,000(円) ③60,000(円) ④140,000(円) ⑤34,230(円) ⑥101,200(円)
①:扶養控除ですね。奥さんは収入がっつり得てますから1人分ですよね。38万円です。09.所得控除p267
②:(c)に対する所得税額。まず所得額は(a)-(b)で、(a)は問58で出ていますし、(b)は表に載っています。それを速算表で計算するだけです。ほんとは簡単なんですけど問58を間違っちゃってるとハズレになってしまうんですよねぇ。所得金額調整控除がねーあったからねー。計算式としてはこう↓
(1270万円-250万円)×33%-1,536,000円=1,830,000円
所得税額が確定しました。総所得をしっかり出せたかどうかで決まる問題でした。
③:配当控除です。ここまでで配当についていろいろ出ていますが、それは配当の所得金額について決めるものでした。ここは税額控除としての配当控除です。10.税額控除p274をご覧ください。これちょっとややこしいんですよね。課税総所得が1,020万ですね。配当は70万でした。てことは70万×5%=35,000円やん!ってなったかた慌てすぎです。1,020万には配当の70万も含まれてますよ!配当所得以外の所得は950万円です。ということは、50万は10%、20万が5%の控除になるので・・・。
50万円×10%=5万円
20万円×5%=1万円
5万円+1万円=6万円となります。慌てないように注意です!(私は本番で一回やらかして落ちた過去がありますwww)
④:住宅ローンですね。まず条件を満たしているか確認。OKです。控除率は今0.7%です。残高2,000万×0.7%=14万円ですね。これは簡単。10.税額控除p274
⑤:税額控除後の所得税(g)に2.1%かけますね。1,630,000×2.1%=34,230円です。
⑥:ここは問題に書いてあるとおり。(i)-(j)です。(i)は(g)+(h)なので、1,630,000+34,230=1,664,230です。よって1,664,230-1,562,940=101,290円。よっしゃ!ってこのまま書いたらハズレです。毎回言ってますが、空欄⑥については100円未満を切捨てよと問題文に書いてますので、101,200円。これが正解です。問題文を落ち着いてしっかり読む!大事にしていきましょう٩( ''ω'' )و
前問から繋がってくる計算問題なので、ひとつこけるとズルズルやられちゃいますね。単独で当てることができる①③④は当てておいてほしいところ。確定点3点にしておきましょう。最低でもここは押さえておいて欲しいという意味で(^^)/
第3問のまとめ
第3問の確定点は12点です。でも控えめにつけての12点なのでもっと高い人もいたかな?12点押さえておけば充分合格ラインと思います。
第4問:不動産
不動産を相続したAさんからの相談。
問60
都市計画法と建築基準法と固定資産税に関する問題。バリエーション豊富。
配点予想は各1点ずつの合計6点。
答 ①高度(地区) ②道路(斜線制限) ③3分の1 ④5分の1 ⑤200(㎡) ⑥4分の1(未満)
Ⅰ:建築物の用途制限および高さ制限
①:高度地区と高度利用地区がありまして、高さに関するのは高度地区です。記述式問題にしてはマニアックで難しい( ˘•ω•˘ )
②:道路斜線制限ですね。これは他の制限が伏字になったなかったのでやさしい問題でした。書きやすいよね(^^)/
07.都市計画法p340
08.建築基準法(道路・用途・高さ)p344
Ⅱ:容積率算定上の延べ面積への不算入
③:建物全体の3分の1を限度に算入しないですね。
④:車庫は5分の1ですよね。この2つは基礎編対策でも暗記しているハズ。楽勝の2問でしたね。
Ⅲ:固定資産税
⑤:200㎡まで6分の1。これも定番で頭に入ってますよね。
⑥:4分の1未満は該当しないが正解です。これ、試験対策的には4分の1以上なら何%でー、2分の1以上なら何%でーって、該当する時の事しか覚えてないのでこういう問われ方するとピンとこない可能性ありますよね。出題の仕方がうまいですな(; ・`д・´)
満点もいけそうではありますが、ここで落とすとしたら①と⑥ですかねぇ。確定点4点にしましょう(^^)/
問61
課税長期譲渡所得の問題です。今回は空家パターンと取得費加算パターンを比較せよとのこと。
ですが今回は共有持分で3分の1所有ですって。いろいろ考えてきますねぇ(*´Д`)
配点予想は①4点②4点③2点でそれぞれ部分点ありの合計10点です。
答 ①8,600,000(円) ②25,480,00(円) ③1,747,000(円)
①被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
これはFPWiki応用編対策の②空き家3000万特別控除パターンで解きます。ですが今回これだけではありません。14.居住用財産の譲渡の特例p367をご覧ください。相続人が3人いる場合、控除額は3,000万円ではなく2,000万円が上限になります。新出です。また、空家3000万パターンは各種特例が使えないのも注意です。ここでは相続税の取得費加算特例が使えません。これらに注意して進めていきましょう。
まずは財産を3分の1にしようね。
9,600万円÷3=3,200万円
これをいつもの式にあてはめましょう。取得費不明なので5%で計算します。
ここで先ほどの注意点。相続人が3人以上いる場合は令和6年から、一人2,000万円までになりました。つまり今回の控除額は2,000万円です。
課税所得=32,000,000-(32,000,000×5%+5,400,000÷3)-20,000,000=8,600,000円
譲渡所得金額は860万円です。2000万になるケースがついに出題されましたね。今まではテキスト本編のみ記載で、応用編対策ページにまでは載せていませんでしたが、来年度版からは掲載いたしたいと思います。2025年版ご利用者はお手数ですが、kindleならメモ機能、書籍の方は書き込んでご利用ください!m(_ _)m
14.居住用財産の譲渡の特例p367
02.課税長期譲渡所得の計算p483
②相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)
これはFPWiki応用編対策の相続税の取得費加算の計算を使って相続時に支払った相続税を取得費用に加えます。取得費は不明なので概算取得費。つまり概算取得費とこの相続税の取得費加算、それと譲費用の3つが控除できるわけですね。こっちを使うと空き家3000万は使えません。
まずは財産を3分の1にしようね。
9,600万円÷3=3,200万円
さて相続税の取得費加算額は=相続税×(評価額÷課税価額)が式です。これを課税所得計算に盛り込みます。Aさんが払った相続税は780万、評価額は持分で2600万、課税価額は6500万円ですね。780万×(2600万÷6500万)ですね。
課税所得=32,000,000-(32,000,000×5%+5,400,000÷3+7,800,000×(26,000,000÷65,000,000))=25,480,000円
空き家3000万の方と比べるとかなり高いですね。どちらを選ぶかはかなり重要なことなんですね。
③所得税および復興特別所得税、住民税の合計額
まずは所得税と復興特別所得税。
8,600,000×15%=1,290,000円
1,290,000×2.1%=27,090円
足し合わせます。
1,290,000+27,090=1,317,000円(100円未満切捨て)
所得税が終わりました。次は住民税。
8,600,000×5%=430,000円
最後は所得税と住民税を足し合わせます。
1,317,000+430,000=1,747,000円
ここは定番ですね。所得税の時に100円未満の切捨てをするクセをつけておきましょうね。
今回は新出の相続人3人がありましたので満点は難しいかも。知識としては学んでると思うんですが、計算問題と脳内リンクできたかどうか。ここは部分点ありの確定点5点といたします!!
02.課税長期譲渡所得の計算p483
14.居住用財産の譲渡の特例p367
問62
乙土地での耐火建築物建築についての問題。配点予想はいつもだと3点ずつにしてるのですが、今回問題数の関係もあるので、2点ずつの合計4点にしてみました。前回もだったかな?最近ここの第4問は問題数増えているのかも( ˘•ω•˘ )
答 ①340(㎡) ②996(㎡)
①建蔽率の上限となる建築面積
今回は第一種中高層住居専用地域(甲土地①とします)と近隣商業地域(甲土地②とします)にまたがる土地です。
指定角地で耐火建築ですので+20%で計算します。甲土地①は80%、甲土地②は100%ですね。接する道路はすべて4m以上なのでそのままでOK。
甲土地①20×15×80%=240㎡
甲土地②20×5×100%=100㎡
240㎡+100㎡=340㎡です。
ここは簡単でしたね。
②容積率の上限となる延べ面積
容積率計算です。今回「特定道路による容積率制限緩和」があります。70m以内に15m以上の道路があって、接する前面道路が6m以上12m未満の時に使えます。「前面道路の幅員による容積率制限」で計算する際に前面道路を太くして計算できます。そして、指定容積率で計算した場合と比較して低い方が採用されます。そして地域がまたがる場合はそれぞれで計算して足し合わせます。
特定道路の制限緩和:(12ー前面道路幅)×(70-特定道路までの距離)÷70=前面道路に加算できる数値
(12ー6)×(70-63)÷70=0.6
甲土地①
(6m+0.6)×4/10=264%
264%より200%が小さいので200%が採用されます。
300㎡×200%=600㎥
甲土地②
(6m+0.6)×6/10=396%
指定容積率400%より小さいので396%が採用。
100㎡×396%=396㎥
最後足し合わせます。
600+396=996㎥
ここも難しくはありません!初心者が間違いやすいのは敷地面積ではなく建築面積を掛けちゃう事。イージーミスしないようにね♪確定点4点!!
04.建蔽率/容積率の計算(p492)
第4問のまとめ
確定点13点。今回、新出がありましたので少し点数ひかえめ。でも充分当てられる第4問でした!
第5問:相続事業承継
最終第5問は「相続税の総額計算」になりました。前回は「類似業種比準価額と純資産価額計算」でした。交互にきてますね。相続税計算も時間が掛かる長丁場!!最後です!乗り切りましょう!!٩( ''ω'' )و
問63
小規模宅地の計算です。ここでの注意点は毎回「減額後の評価額を求めなさい」ではなく「減額される金額を求めなさい」なんですよ。なんで?わざと?わざとなの?
今回は配点予想を3点としました。
答 3,680(万円)
併用する場合は以下の式を用います。
特定事業用等宅地(400㎡限度)×(200÷400)+特定居住用宅地(330㎡限度)×(200÷330)+貸付事業用宅地(200㎡限度)≦200㎡
相続対象は特定居住用が231㎡、貸付事業用宅地は410㎡+540㎡=950㎡です。特定事業用宅地はありません。居住用はフルで使えますね。
4,000万円×80%=3,200万円
貸付事業用宅地で使える枠を算出するためさきほどの式を使います。
特定居住用宅地(330㎡限度)×(200÷330)+貸付事業用宅地(200㎡限度)≦200㎡
231×(200÷330)+X=200㎡
X=200-140
貸付事業用宅地限度=60㎡
貸付事業用宅地の60㎡分は50%減にできます。
さて、マンション甲乙の敷地評価額が伏せられていますので計算いたしましょう。マンションなので貸家建付地。
貸家建付地の価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
マンション甲=8,000万円×(1-60%×30%×100%)=6,560万円
マンション乙=1億800万円×(1-70%×30%×100%)=8,532万円
高い方に適用したいのでそれぞれ計算してみましょう。
マンション甲=6,560万円×(60÷410)×50%=480万円
マンション乙=8532万円×(60÷540)×50%=474万円
意外にもマンション甲が有利です。甲に適用します。
3,200万円+480万円=3,680万円
かなり体力を使う小規模宅地の計算でした・・・。
前々回の試験で登場した時もでそうでしたが、3つの併用式が頭に浮かばないと戦えませんね。そして今回はさらにマンション甲乙を登場させて時間を奪う作戦。なかなか精神を削る攻撃です。集中力を持続することも重要なポイントですね。
ここは取って欲しい。FPWikiの学習知識であれば充分当てられます。ですが確定点は0点といたしましょう。それでも合格ラインは確保できるハズ!!
18.不動産の評価(相続税評価額)p451
19.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例p456
06.相続税の総額計算p502
問64
相続税の総額計算。ここが最大の山場です!!がんばって!!
予想配点は①②各5点で合計10点(いずれも部分点あり)です。
①9,220(万円) ②640(万円)
①相続税の総額
相続税の総額計算では、一旦それぞれの実際の取り分とかは考えずにすべての課税価格から基礎控除をして、法定相続人が法律どおりに受け取ったらいくらになるかで計算します。課税価格の合計額が4億円である場合と問題文にありますので、これを基礎として進めていきます。
まず法定相続人数ですが3人(妻B・長男C・長女D)です。基礎控除額を計算します。今回孫とか養子とかいないから楽かなぁ?
3000万+(600万×3人)=4,800万円
合計課税価格から控除します。
4億₋4,800万=3億5,200万円
この3億5,200万円を相続人が法定相続分で受け取っていきます。問題用紙の相続税の速算表を使います。
妻B:3億5,200万×1/2×40%-1,700万=5,340万円
長男C:3億5,200万×1/4×30%-700万=1,940万円
長女D:3億5,200万×1/4×30%-700万=1,940万円
これらを足し合わせると相続税の総額の完成です。
5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円
相続税の総額は9,220万円となりました。
②長女Dさんの納付すべき相続税額
次は長女Dが実際に相続税をいくら負担すればよいかを計算していきます。
長女Dは4億円の相続財産のうち、1億2,000万円を相続しています。相続税の総額は9,220万円です。
9,220万円×(1億2,000万円÷4億円)=2,766万円
特に何もない人ならここで終わりなんですが、長女Dさんは贈与税の非課税制度を使って4,000万円先に贈与を受けています。非課税制度によって1,000万が控除されて3,000万円が対象に絡んできます。
4,000万-1,000万=3,000万円
更に相続時精算課税制度を受けていて先に3,000万円に対しての贈与税を支払っているんですね。相続時精算課税制度では2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税を支払います。ですからこの分は支払わなくてもいい部分になるので差し引くことになります。ただ忘れてはいけないのが最近の改正で基礎控除110万も使えるようになったこと。これも計算する際に加味しなくてはなりません。ここでイライラするのが長女Dは両親から援助を受けている事。110万を按分して控除してた訳なんで、父からもらった分だけ今回の相続税と絡めるわけですよ。めんどくさ。こんなん買ってもらったようなもんやろ!長女D!!
110万×(3,000万÷(3,000万+3,000万))=55万円
55万円控除されています。
(3,000万-2,500万-55万)×20%=89万円
これが先に支払ってた贈与税額です。この分はさっきの計算で出た相続税額から引いていいわけです。
2,766万円-89万円=2,677万円
以上となります。前々回の解説で↓
「相続時精算課税制度は今後は基礎控除110万円と併用になってくるので、この問題は計算がややこしくなりそうですよね・・・:;(∩´﹏`∩);:」
って言ってたら本当にそうなっちゃったよ(ノД`)・゜・。
問64まとめ
①は基本的な相続図で当てやすかったと思います。②は恐れていた相続時精算課税制度がらみ。今回初回ですから部分点が行ければ良しとしたいですね。
確定点は7点といたします(^^)/
06.相続税の総額計算p502
03.直系尊属からの贈与3種p397
05.相続時精算課税制度p404
問65
最後は穴埋め問題です。よしやるぞ!と思ったらまさかの法定相続情報証明制度かぁ・・・。テキストに入れなきゃいけないのかなぁ。過去に基礎編で1回出題された事はあるんですが・・・。もうひとつは教育資金贈与の非課税ですね。予想配点は各1点の合計7点です。
①法定相続情報一覧図 ②5(年間) ③30(歳) ④1,500(万円) ⑤1,000(万円) ⑥23(歳) ⑦5億(円)
Ⅰ:法定相続情報証明制度
①:法定相続情報一覧図ですね。これは銀行関係者ならすぐわかるんだけどねぇ。
②:登記所の保存期間は5年間。テキスト範囲外だと当てずっぽうで書くしかないよね(ノД`)・゜・。
Ⅱ:直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
③:受贈者は30歳未満が対象です。
④:上限は1,500万円です。学校以外の教育費だと500万円です。
⑤:収入は1,000万円を越えてはいけません。
⑥:23歳未満だったら加算されずに済みます。
⑦:5億円越えちゃったらみなされちゃいます。
03.直系尊属からの贈与3種p397
Ⅰは外してしまっても仕方なし。Ⅱについては頻出の贈与3種の内のひとつですし、全部テキスト掲載なので当てないといけないところ。ですが確定点は受検者目線で最低限ここはってところで考えます。それでいくと⑥⑦は少し難しかったですかね?最終問題は疲れもでるところ。ここは確定点3点としておきます!
第5問のまとめ
確定10点。だいぶ辛口になってしまいました。でもこれは「最低限このくらいは取っておいてね」っていう点数。合格ラインに届けば良しなのです。
応用編まとめ
ここだけは押さえて欲しい点である「確定点」を集計してみると、以下のとおりになりました!(カッコ内は前回試験)
- 第1問 18(14)
- 第2問 15(16)
- 第3問 12(17)
- 第4問 13(17)
- 第5問 10(18)
合計 68(82) 点
ほうほう。今回は少し渋めにつけましたが、それでも68点はしっかり合格ラインですね。FPWikiテキストを網羅した方なら+10点は楽にいけていたと思います。テキスト外が少々出たのと、初出計算問題が少し難度を高くした印象ですね。それと、実際に本番に向かった人は基礎編のテキスト外攻撃をくらってダメージを受けたあとなのでキツかったのはあるかもしれませんね。加点の比重としては第1問が一番高くて徐々に下がっていくというわかりやすい結果に(>_<)
後半戦えるようにスタミナをつけるのも大事ですね!
計算問題はパターンを覚えるのが基本。身体に覚えさせてしまえば体力温存も容易になります。繰り返しやっておぼえていきましょう٩( ''ω'' )و
「基礎編・応用編」総評
基礎編まだ見てない方はこちら→2025年9月実施FP1級学科試験分析(基礎編)
基礎編は、易問22 普通問15 難問13でした。
今回の基礎編は癖ツヨツヨで、絶対当てさせません問題が多く、逆に簡単すぎる易問も多く、なんじゃこりゃーっと振り回されるような回でしたね。
みんな基礎編でぐったり疲れちゃったんじゃないかなぁ。
「確定点」は易問を全問正解、普通問を半分正解、難問は25%正解として66点(四捨五入)!!
応用編については初見問題が穴埋めにも計算問題にもあり、特に計算問題の初出は動揺するので加点が難しかったかもしれませんね。
最終結果は66+68=134点
前回や前々回のような高得点回ではありませんが、しっかりと合格圏となりました。良かった。FPWikiの存在が危ぶまれるかと思った。
実際すべて分析して集計してみると、やっぱり毎回毎回基礎をしっかりしておけば合格点に届くんですね。FP1級に裏技無し!!
効率的なテキストでじっくりしっかり積み上げていけば勝利はあなたに微笑みます!!
合格率ですが、今回は少し下がりますかねやっぱね。10%付近かなぁ。10%未満ってことは無いと思いますが・・・。
合格したみなさん、おめでとうございます!!動揺せずに落ち着いて冷静に取り組める優秀なFPだと思います(^^)/
残念だったみなさん、FP試験はまだまだ続きます!1度の試験で受かろうと思わずに、試験回も学習スケジュールに組み込んじゃってください!
1回で合格するほどFP1級は甘くない!!だからこそ尊いのです!!
次は1月試験。政治も大きく変わっていきますから、この先いろいろと制度も変わっていきそうですね。
わたしも頑張りますので受検生のみなさんも頑張っていきましょう!!みんなで楽しくいきましょう!!
※急ピッチで仕上げましたのでコピペでおかしくなっていたり間違っている箇所がありましたらお問い合わせ・DM等でお知らせください。前回コピペでオオボケかましてたんですが自分で気づいて直しました。気づいた方ご遠慮なくお知らせください~~~m(_ _)m